100年前の大磯 関東大震災特集15 インフラの復旧
今回は、インフラの復旧を特集します。鉄道については、関東大震災特集10駅と鉄道でご紹介しましたので、ここでは、道路や電話、電信、電気の復旧の様子について、助役日誌と警察署の日誌からまとめます。
電信・電話の復旧
電話・電信設備の壊滅的な被害により連絡手段を失った警察署では、直接現場に行くか、報告を待つしかありませんでした。特に電話の復旧は急務で、警察と軍関係の電話架設を急ぎ行いました。平塚の海軍火薬廠と平塚警部補派出所との特別電話の架設(9月3日)、警察駐在所間の電話の開通(9月5日)、応援に駆け付けた軍本部(中郡役所に駐在)と警察間の架設(9月9日)が行われました。電話は、災害の情報収集や救護、警察と軍との連携などに必要な、大切な連絡手段です。一般向けの電話架設工事に着手したのは23日以降となります。
注:この当時の電話普及率はかなり低く、軍や役所、店舗や医院などが主でした。電話交換手を経ての通話、さらに当時の電話代は、例えば東京~横浜間の5分の通話料金が15銭(現在の約2,200円)と高く、気軽なコミュニケーション手段ではありませんでした。当時から公衆電話は設置されていたようです。
電信(電報)は、電話が普及する前からあった文書配達サービスのことで、郵便局が行っていました。現在ではインターネットの普及によりSNSや電子メールに取って代わられていますが、かつては電報は一番早い連絡手段でした。震災では、大磯と二宮の郵便局の電信設備が全て破壊されてしまいました。二宮局のみがようやく回復し、震災後初めて届いた電報第1報は19日でした。大磯局の回復に関してはっきりした記述はありませんが、10月8日に軍の電信隊が来磯、西小磯に宿泊したことが記載されていることから、電信工事のために来たのかもしれません。
電気の復旧
当時、一般家庭では、電球1個を使うと月額3~4万円の電気代がかかり、電気はとても高価な物でした。 そのため、電灯を使う家庭はそれほど多くなく、石油ランプが主流でした。しかし、役所や主要道路では電灯が使われていました。
平塚の海軍火薬廠には火力発電の設備があり、電力提供の朗報が届きました(9月4日)。翌日には、平塚町、須馬村、大野村の街路と重要な箇所が点灯され(5日)、海軍火薬廠と小田原電灯会社の工夫により、大磯町内の20数か所と大磯警察署内2か所の電灯の点灯(6日)、吾妻村から国府村の東海道沿いの点灯(7日)、吾妻村の要所の点灯(8日)、と徐々に電気が復旧しています。大磯町では山手と海岸方面、大連隊本部に電灯を架設し(9日)、さらに各家庭の電灯についても、2~3戸に1灯の割合で点灯する計画が立てられました。
日々復旧が進み明かりが増えていくにつれて、町民たちは復興の明るい希望を感じたのではないでしょうか。
小田原電灯会社(水力発電)からの送電が復旧したので、火薬廠からの電気配給は必要なくなりましたが、震災直後から火薬廠の応援と協力は大変ありがたいことだったと思います。電力だけでなく、ろうそくの代用品としての原油70貫(約260キログラム)の寄贈(9月9日)、玄米を精米するための電動精米機の貸出より(9月8日)、小見助役たちは連日、米の廉売をして、避難者や被災者の食を確保することができました。
10月4日には藤田町長より、海軍火薬廠に感謝状が贈られています。
道路の復旧
震災以降、寸断された交通網により人や物の運搬が滞り、復旧が急務でした。9月1日当日、大惨事となった列車転覆事故の応援要請の書面を届けるため、警察署は、自転車にて横浜の県庁に使いを向かわせました。鉄道は不通、橋の崩壊、道路が寸断された中でどのようにしてたどり着いたのでしょうか。当然、横浜でも大変な被害が出ていたことは知る由もありませんでした。
震災直後から、太平自動車商会による花水川~大磯(警察署付近、当時は現在の大磯町消防署に位置)間の輸送、伊勢原自動車株式会社による馬入川~平塚町間の輸送、荷馬車と貨物自動車による大磯町~国府村間の輸送を、全て無料で開始しました。
道路の復旧工事は9月5日から開始しています。警察署の日誌には「各道路の亀裂が激しく、路面には家屋が倒壊し、交通が完全に遮断している状況であるため、一般通行人の利便と、物資の輸送に利用するため、消防組員を数名配属して、特別に開通工事にあたらせた。付近住民もこれに賛同して協力、援助した」と記され、平塚~大磯間の道路の大部分を復旧することができました。
そして、引き続き大磯~吾妻村間の道路の復旧が続けられます。16日には、二宮~秦野間の道路が復旧し、乗合自動車を走らせました。
インフラの被害は生活上の影響が大きいため、急ぎ対応を開始し、想像以上に復旧は早かったのではないかと思います。軍隊の応援、在郷軍人、町役場職員や警察官、消防組合員、地元の人たち等、復興を願う大勢の人たちの気持ちと力を感じます。
次回は1月26日(金曜日)に更新します。学校の被害と復旧について特集します。
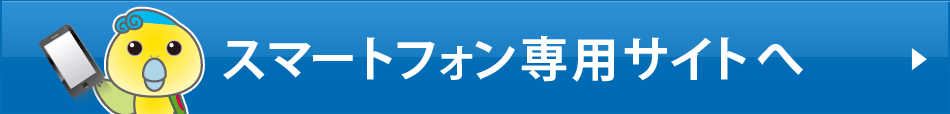







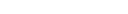
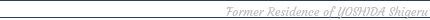




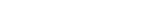



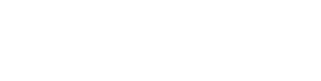
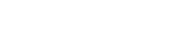
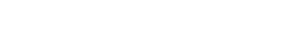



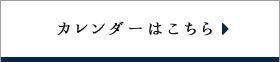
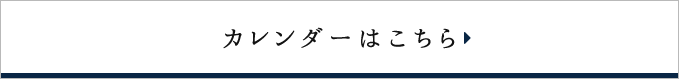
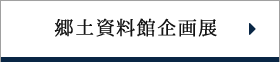
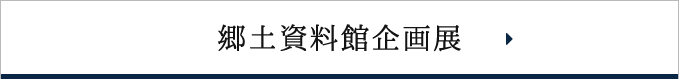
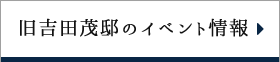
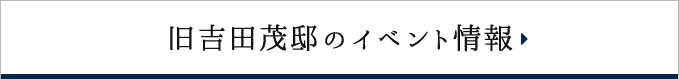
更新日:2024年01月19日