100年前の大磯 関東大震災特集14 港と海水浴場の復旧
大磯における関東大震災の被害の一つに地盤の隆起があります。この現象により、大磯の要である港と海水浴場が、大きな打撃を受けました。
助役日誌の9月1日の記事には、
「突然震動が起こり、続いて未曾有の大地震となり、小さい津波を起こし、すぐに異常な引き潮を起こした」
とあります。
また、大磯警察署の日誌には、この現象を検証するために、9月9日に中央気象台の中村博士が随員と共に来署し、大磯及びその付近を視察した上で、次の談話をしたと書かれています。
「震源地は、大島西の方の海中で、当地や房州地方は地盤が著しく隆起し、横浜・東京方面はやや沈下した。つまり、大磯町・平塚町で海水が減退したのは、地盤が隆起したためであり、海水が減ったわけではない。なお、津波や地震のおそれは絶対にない」
大正関東地震の震源
大正関東地震(関東大震災)の震源については、特集記事3「大正関東地震の発生メカニズム」でも紹介しましたが、この地震によって、大きな揺れは3回起こりました。 近年の研究によると、関東大震災を起こした本震は、小田原の北約10キロメートルの内陸で、地震の規模はマグニチュード7.9でした。余震は2回起きており、
- 最初に発生した地震の5分後に、相模湾の真中でマグニチュード7.3
- ほぼ1日後に、房総半島の南東約20キロメートルの所でマグニチュード7.3
が発生しています。
つまり、大きな揺れは、合計3回起こっていることになります。(この他にも、規模の小さな余震は、たくさん起こりました。)
隆起した海岸
気象庁のホームページによると、津波は、海底下で大きな地震が発生することによって発生するとあります。 この考えを関東大震災に適用すると、津波は、本震から5分後に発生した大きな余震により起こったと考えられるでしょう。そうすると、9月9日に視察した、中央気象台の中村博士の考えは正しいと言えそうです。つまり、大磯では、最初の内陸で起こった本震で地盤が大きく隆起して海底が現れ、海底が現れた理由は、津波による海水の引きではなかったのではないでしょうか。
関東大震災では、房総半島や湘南地方を中心に土地の隆起が起こり、もっとも隆起が激しかったのは房総半島南端から大磯付近を巡る一帯でした。大磯では海底が2メートルほど隆起しました。助役日誌に、「すぐに異常な引き潮を起こした」とあるのは、津波の影響ではなく、この海岸の隆起によるものだったのでしょう。
海水浴場と港の復旧
この隆起現象は、海岸に磯が突出して、漁船の発着や海水浴に影響を与えました。そのため、大磯水産会や海水茶屋(現在の海の家)は、港と海水浴場の復旧工事を働きかけます。この要請を受けて、町は県費の補助を得て、次のような復興計画を立てました。
- 南浜海岸、北浜海岸を浚渫(しゅんせつ)し、南浜海岸に大型漁船、北浜海岸に小型漁船の船揚場をつくる。
- 暗礁を干潮面に2メートル以下になるよう掘削し、北浜に点在する3つの岩礁を結んで防砂壁を造成する。
町は大磯漁業組合と取り決めを結び、工事は漁業組合が主体となって実施、設計や監督は県に委託しました。工費は11万円(現在の約2.2億円<注>)で、県費の補助のほか、5万円を国庫補助、1万800円を町が補助しました。
注
当時、米10キログラムの値段は約2円でした(『国史大辞典』12、「米価」の項による)。こちらの記事を執筆した現在、米10キログラムは4,000円で購入できました。従って、1円=2,000円の価値があったと考えられます。この計算によって、11万円×2,000円=2.2億円と算出しています。(2025年1月23日訂正・更新)
この工事は、大正14年(1925年)2月20日に着工され、7月半ばに竣工、この年の海水浴に間に合ったのです。
次回は1月19日(金曜日)に更新します。インフラの復旧についてまとめます。
参考
- 『大磯町史』7、2008年、p.456~458
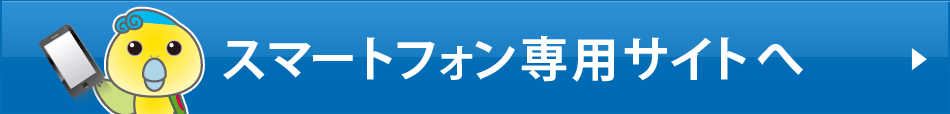







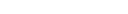
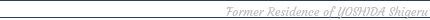




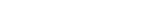



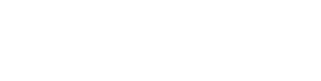
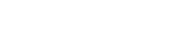
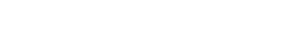



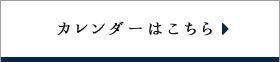
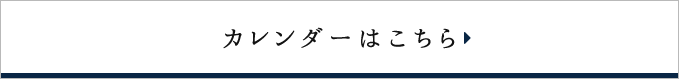
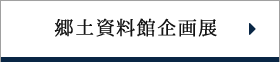
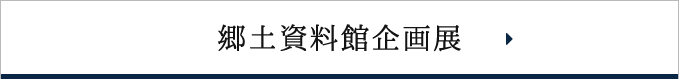
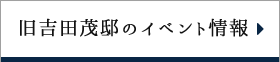
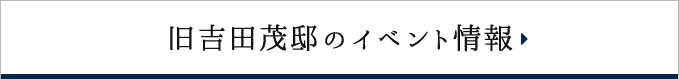
更新日:2025年01月23日