大正13年12月4日
12月4日(木曜日)、午前8時40分出勤。
本日出勤前、自宅において知人より、町長辞意の善後策を交渉中であることを聞き取った。
午前10時頃、本県属の宮下玉吉氏が徴兵旅費繰替の件で来場したので、渡辺主任書記と佐藤書記が立会い、午前11時に退場された。
本日、小学校応急資金利子について、大正18年3月31日までの分は無利子とし、大正33年8月20日限りで、利子払い込みの分は返すとの通知があった。義務教育費国庫負担金の配金額は、大正13年度の教員に対する分として948円74銭、児童数に対する配当金は1,159 円98銭、合計金2,108円72銭である。(11月交付と2月交付の合計半額ずつ)
午後3時頃、高麗神官が、伊勢神宮太麻の配布にあたり、頒布式を役場において各区長を召集し行われた。助役も参加した。
本日、藤田町長と面談した。
午後4時に退庁した。
午後7時頃、佐藤書記が、三島子爵の祖母である和歌子氏の死亡並びに葬儀を知らせるため、小生の自宅を訪問してきた。
解説
町では、震災で倒壊した小学校を再建するための資金の多くを、借り入れで賄っていました。その利子が当初の計画より減額され、返済金があると通知が来たようです。
また、「義務教育費国庫負担金」とは、義務教育にかかる経費を国が負担するということです。学制が発布された明治5(1872)年当初は、住民や保護者が授業料を負担し、その後、授業料が市町村負担となっていきました。しかし、明治33(1900)年、義務教育の無償制が実施されると就学者が激増して市町村財政は過重となり、教職員の処遇が悪化する事態が起こりました。そこで、大正7(1918)年に「町村義務教育費国庫負担法」が制定され、国と地方で分担するようになりました。今日の日誌には、その金額の詳細が記されています。
午後には、高来神社の神官が、「伊勢神宮大麻」(たいま)の頒布式を、区長を集めて行っています。これは「伊勢神宮の御札」を、新年を迎えるにあたり頒布する儀式で、毎年行われていました。
また、帰宅後、書記が知らせてきたのは、故三島通庸子爵(みしまみちつね)の妻である和歌子の訃報です。享年78歳でした。三島通庸は、明治政府において、様々な分野で活躍し、明治21(1888)年、警視総監在任中に亡くなりました。大磯地区に別荘を構えるなど、大磯とゆかりのある人物です。三島が亡くなったのち、和歌子は12人の子どもを育て、長男弥太郎は日本銀行総裁に、五男の弥彦はマラソン選手の金栗四三と共に、日本人初のオリンピック代表選手になりました。また娘達の婚姻で、姻戚関係も広がり、その中には牧野伸顕と吉田茂がいます。ちなみに、この時の三島子爵とは孫の三島通陽(みしまみちはる)のことです。
辞意を伝えてきた町長の後任について、水面下なのでしょうが動きはあるようです。どうなっていくのでしょうか…。
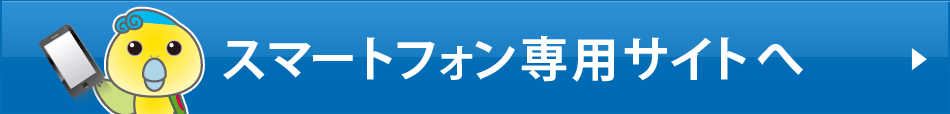







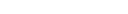
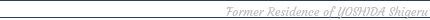




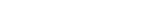



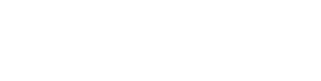
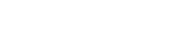
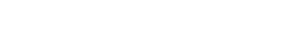



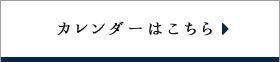
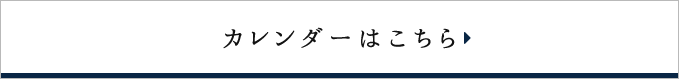
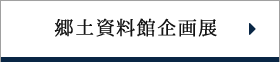
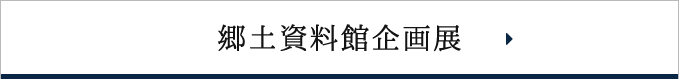
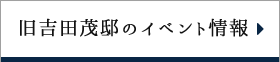
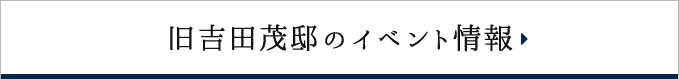
更新日:2024年11月12日