選挙に関するQ&A
選挙権について
Q1:満18歳になれば誰でも投票できるのか。
A1:日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。ただし、地方公共団体(都道府県や市町村)の選挙については、その区域内に引き続き3か月以上住んでいることが必要となります。選挙権を持っていても、実際に選挙で投票するためには、市町村が作成する選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
⇒「選挙権と被選挙権」
Q2:どうすれば選挙人名簿に登録されるのか。
A2:選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で大磯町の区域内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていることが必要です。(大磯町内で転居した場合は通算されます。)
他の市町村から転入された方については、役場町民課で「転入届」を提出する必要があります。
⇒「選挙人名簿と登録」
Q3:選挙人名簿に登録される時期は。
A3:選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で登録される資格のある方を登録します。また、選挙が行われる時も登録の基準日及び登録日(公示(告示)日の前日)を定めて登録します。
⇒「選挙人名簿と登録」
Q4:選挙人名簿の閲覧はできるのか。
A4:選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。(ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。)
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
⇒「選挙人名簿と登録」
Q5:選挙人名簿から抹消されることはあるのか。
A5:以下のような場合に抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を失ったとき
- その市町村から転出して、4か月を経過したとき
- 在外選挙人名簿へ登録の移転をするとき
- 誤って登録されていたとき
⇒「選挙人名簿と登録」
投票について
Q1:投票所入場整理券(ハガキ)がなくても投票できるか。
A1:投票所入場券(ハガキ)を紛失した場合やお手元に届かなかった場合等でも、選挙人名簿と照合し、ご本人と確認できれば投票できますので、投票所(期日前投票所)の係員にお申し出ください。また、投票所入場券が届いても、投票資格を失った場合には、投票することはできません。
⇒「投票について」
Q2:投票所での本人確認の方法は。
A2:投票に来られた方が、ご本人であることを確認するため、誕生日などをおたずねしています。万一、別人が本人になりすまして投票すれば、なりすまされた人が投票できなくなってしまうためです。ご理解、ご協力よろしくお願いします。
Q3:投票所は何時まで開いていますか。
A3:投票日当日の投票所は、原則午前7時に開き午後8時に閉じます。期日前投票所は、原則午前8時30分から午後8時までです。投票所・期日前投票所によって異なる場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
Q4:旅行や出張などで投票日当日に投票に行けない場合はどうすればよいのか。
A4:投票日当日に、旅行や出張などで投票所に行けないときは、期日前投票制度や不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することができます。
⇒「期日前投票」
Q5:病院に入院している場合や老人ホームに入所中の場合はどうすれば投票できるか。
A5:入院(入所)中の病院や老人ホーム等が、都道府県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定を受けていれば、その施設内で投票できます。現在、入院(入所)中の施設が不在者投票できる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続等については、各施設におたずねください。
⇒「病院・老人ホーム等での不在者投票」
Q6:身体に障害があるため、自宅で投票したいがどうすればよいか。
A6:身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持つ人で一定の障害がある人、介護保険の被保険者証を持つ人で要介護5の人は、自宅で投票用紙に記入し、郵送する不在者投票ができます。(一時的に歩行困難となって自宅療養をしている場合等は該当しません。)
この「郵便等による不在者投票」をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
⇒「郵便等による不在者投票」
Q7:外国に住んでいても投票できるか。
A7:国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるため「在外選挙制度」があります。
国外で選挙を行うには、町の在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を持っていれば、衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で投票することができます。
在外選挙人名簿への登録の申請には、以下の2つの方法があります。
- 出国後に居住している地域を管轄する日本大使館、総領事館等に申請する方法
→(在外公館申請) - 国外転出する時に、選挙人名簿に登録されている人を同一の市区町村の在外選挙人名簿に移転するために、国内で申請手続きを行う方法
→(出国時申請)
⇒「外国にいても日本の国政選挙の投票ができます(在外選挙制度)」
Q8:身体が不自由な人などが投票するための制度には、どのようなものがあるのか。
A8:次のような方法で投票することができます。
- 点字投票
視覚が不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
点字投票を希望される人は、点字用の投票用紙と点字器をお渡ししますので、投票所の係員に申し出てください。 - 代理投票
身体が不自由などの理由で、自分で投票用紙の記入ができない人は、投票所の係員が代筆する「代理投票」ができます。「代理投票」を希望される人は投票所の係員に申し出てください。
(注)この制度は、本人の選挙権を代理の人(付き添いや家族の介護人など)が代わりに行使するものではありません。本人が投票所に行き自ら投票することが原則です。
⇒「投票で支援が必要な方へ」
Q9:身体が不自由な人などのために、投票所にはどのようなものを置いているのか。
A9:各投票所には、車いすに対応した特別記載台、ルーペ(拡大鏡)、※投票用紙記入補助具、点字器や点字氏名表、投票用紙を記載する際に用紙を押さえるための文ちんを用意しています。
※投票用紙記入補助具
→投票用紙に自筆する際に、記入する枠がよく見えないなど不安がある方が、記入する枠がわかりやすくなるようにご使用いただくものです。投票用紙を入れるカードケースは、記入する枠の部分が切り抜かれていますので、表面を手で触ることで記入する位置がわかるようになっています。
⇒「投票で支援が必要な方へ」
Q10:投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に代筆できるのか。
A10:投票所の管理者が認めれば、選挙人に同伴する補助者・介助者の人は投票所へ入場できますが、これらの人が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。なお、身体が不自由などの理由で、自分で投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙に記載する「代理投票」制度があります。(Q8参照)
⇒「投票で支援が必要な方へ」
Q11:投票所内に候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことはできるのか。
A11:選挙人が自らの備忘録として書いたメモを投票所に持ち込むことは出来ます。しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについてはご遠慮いただいております。
Q12:投票所内で携帯電話を使用することはできるのか。
A12:スマートフォン等の電子機器の持込については、特に制限はありませんが、投票所内での通話や投票所内の撮影など、他の投票人に影響を与えたり、投票所内の秩序をみだすと判断した場合は制限させていただきますので、ご理解いただきますようお願いします。
Q13:小さい子どもも一緒に投票所に入れるのか。
A13:公職選挙法の一部改正により、平成28年度から投票所に入ることができる子どもの範囲が「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。保護者の方などが実際に投票している姿を同伴しているお子さんに見せることで、一票の大切さを学び、有権者になったときに投票に行くきっかけにしてください。
投票所に入るときはルールをお守りください
- 選挙人の同伴する子どもは、投票用紙への記載および投票箱への投函をしないこと。
- 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
- 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
- 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。
⇒「子どもと一緒に投票所へ」
Q14:どのような投票が無効票になるのか。
A14:公職選挙法68条によると、無効票となる主な具体例は以下のような場合です。
(注)比例代表選出議員ではない一般的な公職の選挙の例
・所定の投票用紙を使用していない投票
投票所で交付される投票用紙を用いていない投票
・候補者でないものの氏名を記載した投票
候補者の氏名と全く関係がない氏名が記載されている投票
・2人以上の候補者の氏名を書いた投票
一枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名を記載した投票
・候補者の氏名のほか、他事を記載した投票
他事とは、候補者の氏名を記載した文字以外の記載をした投票
氏名の下に「へ」、「に」、「さんへ」等の記載のある投票は他事記載として無効
(注)氏名のほかに職業、身分、住所又は敬称の類を記載した投票は無効になりません。
・候補者の氏名を自書しない投票
ゴム印等の押印による投票
(注)代理投票、点字投票は自書ではありませんが有効です。
・どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票
記載の不明瞭なものや、2人以上の候補者の氏名の一部を混同して記載したものは無効になることがあります。
・白紙投票、単なる雑事、記号等を記載した投票
白紙や「頑張れ」、「必勝」など、候補者の氏名とは関係ない言葉や記号を書くと、どの候補者の得票にもできないため、無効となります。
(注)書き損じた場合は、二重線で見え消しを行い、空いているスペースに正しい候補者を記載してください。正しく記載されていれば、枠をはみ出しても無効票にはなりません。
立候補について
Q1:選挙にはどのような種類があるのか。
A1:大磯町で執行される主な選挙は次のとおりです。
国政選挙
衆議院議員総選挙
衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区と比例代表選挙の2つからなります。選挙は任期満了(4年)による場合と衆議院の解散による場合があります。また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われます。
小選挙区選挙:候補者1人の氏名を記載。
比例代表選挙:政党などの名称や略称を1つ記載。
最高裁判所裁判官国民審査:あらかじめ投票用紙に裁判官名が印刷されているので、辞めさせた方がよいと思う裁判官名の上の欄に×(×印)を付けます。なければ何も書かずに投票します。
参議院議員通常選挙
参議院議員の半数を選ぶために行われる選挙のことです。選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。参議院に解散はなく任期は6年ですが、3年ごとに半数を改選するよう憲法に定められています。
選挙区選挙:候補者1人の氏名を記載。
比例代表選挙:候補者1人の氏名、または政党等の名称や略称を1つ記載。
地方選挙
地方議会の議員の選挙
都道府県や市区町村の議会議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。任期満了(4年)による場合と議会の解散による場合があります。
候補者1人の氏名を記載。
⇒「投票について」
Q2:何歳になれば立候補できるのか。その他に何か条件はあるのか。
A2:選挙に立候補できる年齢や条件は次のとおりです。
⇒「選挙権と被選挙権」
Q3:立候補するのに必要な供託金はいくらか。
A3:立候補をするためには、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。各種選挙の供託金は次のとおりです。
・衆議院小選挙区:300万円
・衆議院比例代表 候補者1名につき:600万円
(注:候補者が小選挙区との重複立候補者である場合は、比例代表の供託金は300万円)
・参議院選挙区:300万円
・参議院比例代表 候補者1名につき:600万円
・都道府県知事:300万円
・都道府県議会議員:60万円
・政令指定都市の長:240万円
・政令指定都市議会議員:50万円
・その他の市の長:100万円
・その他の市の議会議員:30万円
・町村長:50万円
・町村議会議員:15万円
Q4:供託金は戻ってくるのか
A4:候補者が政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や候補者が立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市町村に納められます。また、選挙運動用自動車や選挙運動用ポスター等の公費負担も受けられなくなります。
・衆議院小選挙区:有効得票総数の10分の1未満
・衆議院比例代表:没収金=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
・参議院選挙区:有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の8分の1未満
・参議院比例代表:没収額=供託金-600万円×比例代表の当選者数×2
・都道府県知事:有効得票総数の10分の1未満
・都道府県議会議員:有効得票総数をその選挙区の議員定数で割った数の10分の1未満
・政令指定都市の長:有効得票総数の10分の1未満
・政令指定都市議会議員:有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の10分の1未満
・その他の市の長:有効投票総数の10分の1未満
・その他の市の議会議員:有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の10分の1未満
・町村長:有効投票総数の10分の1未満
・町村議会議員:有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の10分の1未満
Q5:立候補の届出はいつするのか。
A5:立候補の届出期間は、選挙期日(選挙の投開票日)の公示又は告示のあった日の1日間だけです。また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。選挙管理委員会では町長選挙及び町議会議員選挙の前に立候補予定者説明会を開き、資料や提出書類を配り、記載方法や添付する書類、選挙運動の注意点などを説明します。その後、立候補受付当日に書類の不備等が生じないよう、あらかじめ提出書類の内容をチェックする事前審査期間を設けます。
Q6:選挙の公示日(告示日)はいつなのか。
A6:各種の選挙期日(選挙の投開票日)の公示または告示をすべき日は法律で以下のとおり定められています。(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の場合は、天皇の国事行為として行われるため「公示」と呼ばれ、その他の選挙(衆議院・参議院の補欠選挙を含む)はその選挙を管理する選挙管理委員会が行うため「告示」と呼ばれます。)
・衆議院議員選挙:選挙期日前少なくとも12日前まで
・参議院議員選挙:選挙期日前少なくとも17日前まで
・都道府県知事選挙:選挙期日前少なくとも17日前まで
・都道府県の議会議員選挙:選挙期日前少なくとも9日前まで
・指定都市の市長選挙:選挙期日前少なくとも14日前まで
・指定都市の市議会議員選挙:選挙期日前少なくとも9日前まで
・その他の市長及び市議会議員選挙:選挙期日前少なくとも7日前まで
・町村長及び町村議会議員選挙:選挙期日前少なくとも5日前まで
当選人及び任期について
Q1:選挙(比例代表選挙以外)での当選人はどうやって決定するのか
A1:得票数の多い順に当選人になります。ただし、「法定得票数(Q5参照)」以上の得票がなければなりません。得票数が同数の場合は、くじ(Q4参照)で順番を決めます。
Q2:衆議院比例代表選挙の当選人はどうやって決定するのか。
A2:選挙区(ブロック)ごと政党等の得票数に比例して政党等の投票人の数が決まります。政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
Q3:参議院比例代表選挙の当選人はどうやって決定するのか
A3:各政党等の総得票総数に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。特定枠の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし、名簿記載の順位の通りに当選人となります。その他の名簿登録者については、その得票数の多い順に当選人が決まります。(得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います。)
Q4:選挙で得票数が同数の場合はどうやって当選人を決めるのか
A4:公職選挙法では「当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。」とあります。例えば、町長選挙で法定得票数以上の最多得票数を獲得した候補者が同じ得票数で2人以上いる場合や、町議会議員選挙で法定得票数以上の最下位当選者となる候補者が同じ得票数で2人以上いて、定数を超えることとなる場合は、選挙長がくじで当選人を決定することになります。
Q5:何票獲得すれば、当選に必要な法定得票数に達するのか
A5:事前に何票以上獲得すれば法定得票数に達するということはわかりません。その得票数が、有効投票総数の一定の割合に達している必要があります。一定の割合は選挙によって異なり、以下のとおりです。
・衆議院小選挙区選出議員:有効投票総数の6分の1以上
・参議院選挙区選出議員:有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の6分の1以上
・地方公共団体の議会の議員:有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の4分の1以上
・地方公共団体の長:有効投票総数の4分の1以上
(注意:衆議院・参議院の比例代表選挙に法定得票数はありませんが、衆議院の比例代表選挙で小選挙区との重複立候補者が復活当選するには、小選挙区で供託金没収点(当該小選挙区の有効投票総数の10分の1)以上を獲得しておく必要があります。)
Q6:当選者の任期はいつから始まるのか
A6:選挙で当選した者は、一定の期間、国民(住民)の代表として、その公職として働きます。その期間を「任期」といいます。任期は、衆議院議員は4年、参議院議員は6年、地方公共団体の議員や長は4年です。任期の開始については、以下のとおりです。
・衆議院議員:総選挙の期日から(ただし、任期満了による総選挙が任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了日の翌日から)
・参議院議員:前議員の任期満了の翌日から(ただし、通常選挙が前議員の任期満了日の翌日後に行われた時は、通常選挙の期日から)
・地方公共団体の議員:一般選挙の日から(ただし、任期満了による一般選挙が任期満了前に行われた場合において、前任の議員が任期満了日まで在任したときは、任期満了日の翌日、選挙後に前任者が全てなくなったときはその日の翌日から)
・地方公共団体の長:選挙の日から(ただし、任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合のおいて、前任者が任期満了の日まで在任したときは、任期満了日の翌日から、選挙後に前任者が欠けたときはその日の翌日から)
Q7:長や議員が欠けた場合の繰上げ補充の要件は
A7:繰上げ補充とは、一旦有効になった長や議員となった者が、死亡や辞職などで欠けた場合、補欠選挙を行わないで、一定の資格、要件を有する者を当選人に補充する方法です。なお、繰り上げ当選の対象となる落選者は、得票が法定得票数を超えていなければなりません。(注意:衆議院比例代表選挙で重複立候補をした候補者については、小選挙区で供託金没収点(当該選挙区の有効投票総数の10分の1)を獲得した者)
繰上補充は、選挙の種類に応じ、以下の要件で行われます。
・衆議院小選挙区選出議員、地方公共団体の長の場合
⇒「当選者と同数の票を獲得し、くじ引きの結果落選した者」から
・衆議院、参議院比例代表選出の場合
⇒「同一比例名簿の最下位当選者の次の順位の者(次点者)」から
・参議院選挙区選出議員、地方議会議員の場合
⇒「選挙日から3か月以内…最下位当選者の次の順位の者(次点者)」から
⇒「選挙日から3か月経過後…当選者と同数の票を獲得し、くじ引きの結果落選した者」から
(注意:繰上補充の該当者がいない場合は、都道府県知事や市町村長であれば選挙が実施され、都道府県議員や市町村議会議員では欠損のままか、補欠選挙が実施されることとなります。)
Q8:県知事や町(市)長が在任中に辞職し、再度立候補して当選した場合の任期は
A8:公職選挙法は特例を設け、地方公共団体の長の職の辞職を申し出た者が、その退職を申し出たことによって行われる選挙において再び当選した場合、その者の任期は当初の任務の残任期間となります。(つまり、退職によって執行された選挙はなかったこととみなされます。)
選挙運動と政治活動について
Q1:選挙活動と政治活動の違いを教えて欲しい
A1:公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。
・選挙運動とは:「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為」であるとされています。これは選挙運動期間中にのみ認められます。
・政治活動とは:「政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、「選挙運動」にわたる行為を除いたもの」であるとされています。
Q2:選挙運動期間はいつからいつまでできるのか
A2:選挙運動は公示(告示)日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみ行うことができます。立候補の受付は、午前8時30分から開始されますが、立候補届が受理されないと選挙運動はできません。なお、選挙運動の終期は選挙期日の前日の午後12時までです。
Q3:やってはいけない選挙運動にどんなものがあるのか
A3:以下のような選挙運動は禁止されています。
・戸別訪問(公選法第138条)
何人(いかなる人)も、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。(戸別訪問の類似行為の禁止)
・署名運動(公選法第138条の2)
何人(いかなる人)も、選挙に関して特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し、署名を集めてはいけません。なお、他の署名活動との関係では、議員・長の解職請求など地方自治法に基づく直接請求のための署名収集は任期満了の60日前(衆議院解散の場合は解散日の翌日)から投票日までの間、署名収集活動が禁止されます。(地方自治法第74条、同法施行令第92条)
・飲食物の提供(公選法第139条)
何人(いかなる人)も、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。従って、候補者が選挙運動員や労務者に対し、慰労を目的に飲食物を提供することや候補者や選挙運動員が選挙事務所の来訪者に手料理をふるまうこと、さらに第三者が候補者に対して陣中見舞いを差し入れることも禁止されます。ただし、湯茶及びこれに伴うお茶うけ程度の菓子や果物、漬物等の提供は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
・選挙期日後の行為(公選法第178条)
当選又は落選に関するあいさつをする目的での戸別訪問や、手紙等(自筆の信書を除く。)の差し出し、新聞・雑誌による広報、放送設備による放送、当選祝賀会等の集会開催、また自動車を連ねたり、隊列を組んで往来し、気勢を張る行為はできません。ただし、選挙期日後に自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすることは可能です。
・買収(公選法第221条から223条)
選挙犯罪で最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
Q4:告示前に出陣式の案内状を特定多数に配布することはできるのか
A4:出陣式の案内状は、選挙運動に関する文書図書と考えられ、事前運動の禁止規定に抵触します。
Q5:選挙運動用の自動車の声がうるさいので何とかして欲しい
A5:候補者などが選挙カーから拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも、候補者ができる選挙運動の一つです。午前8時から午後8時まで行うことが認められています。音量の規制は特になく、実際に騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で有権者に政見を訴える一方、有権者にとっても候補者やその政権を知る機会でもありますのでご理解願います。なお、学校、病院、療養施設等の周辺では、マイクの音量を落とすなど、静穏に努めなければならないとされています。
Q6:インターネットを利用した選挙運動について注意点を教えて欲しい
A6:インターネットを利用した選挙運動については、特に次の点に注意してください。(注意:インターネットによる投票はできません。)
・年齢満18歳未満の人はインターネットを利用した選挙運動を含め、選挙運動を行うことができません。
・一般有権者(候補者・政党等以外の者)は、電子メールを利用した選挙運動を行うことができません。(注意:電子メールを使用した選挙運動ができるのは、候補者及び政党等に限られます。一般の有権者は、候補者及び政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを他者に転送することはできません。)
・ホームページや電子メールの文面等を印刷して頒布や回覧することはできません。
・選挙運動期間外に選挙運動を行ってはいけません。(例:投票日当日のウェブサイト等の更新不可)
寄附について
Q1:政治家は選挙区内にある者に対して寄附をすることは許されるのか
A1:政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者をいいます。)が選挙区内にある者(住所に限らず、選挙区内にいる全ての者)に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。ただし、次のものは対象から除外されます。
・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀(物品を含む)
・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典(金銭のみ。花輪、供花、線香等は不可)
(注意:上記2つであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも処罰をもって禁止されています。
⇒「寄附の禁止等について」
Q2:冠婚葬祭や地域のイベントなどに関して、どのようなものが寄附禁止の対象となるのか教えて欲しい
A2:寄附禁止の対象となる主なものは以下のとおりです。
・病気見舞い
・お祭りへの寄附や差入
・地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
・秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝の花輪
・入学祝、卒業祝
・お中元やお歳暮
・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
・氏子や檀家になっている社寺の修繕等に対する寄進やお賽銭など
(注意:政党や親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。ただし、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
⇒「寄附の禁止等について」
Q3:政治家は選挙区内にある者に対して時候のあいさつ状を出せるのか
A3:年賀状、暑中見舞状、残暑見舞状、寒中見舞状、余寒見舞状、クリスマスカード、喪中欠礼葉書などは禁止されています。なお、次のものは禁止されていません。
・答礼のための自筆によるもの(相手方の住所、氏名、あいさつ文、差出人氏名自筆のもの)
・弔電
・各種の大会などに対する祝電
・インターネットのホームページに掲載するあいさつ状
・電子メールで送信されるあいさつ状
ただし、次のようなものは、「答礼のための自筆によるもの」として認められません。
・印刷した時候のあいさつ状に住所と氏名だけを自署したもの
・パソコン等で作成したあいさつ状
・自署したあいさつ状をファックスで送信したもの
・昨年もらった(答申していない)年賀状に対して、今年答礼するもの
⇒「寄附の禁止等について」
Q4:政治家が地元の町内会長として、祭りや運動会の協賛金を募る行為は公職選挙法に違反するのか
A4:公職選挙法第199条の2では、政治家は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもって行うことを問わず、寄附が禁じられています。ただし、禁止されている行為は寄附行為であって、寄附を呼び掛ける行為は制限されていません。なお、公職選挙法第199条の2第3項において、政治家に対し、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し又は要求してはならないとされており、たとえ政治家が町内の自治会長や役員等であっても寄附を求めてはいけません。
その他
Q1:町内の有権者の数はどれくらいか
A1:本町の直近の選挙人名簿登録数はホームページでご覧いただけます。
⇒「選挙人名簿投票区地区別登録者数」
Q2:過去の選挙の投票率を知りたい
A2:本町の過去の選挙(町長選、町議選、県知事選、県議選、衆議院選、参議院選)の投票率はホームページでご覧いただけます。
⇒「投票率の推移」
また、過去の各種選挙の投票率等の選挙結果もホームページでご覧いただけます。
⇒「実施選挙ごとの結果」
Q3:生徒会の選挙で本物の投票箱や記載台を使いたいので貸して欲しい
A3:将来の有権者である児童や生徒が、学校生活の場において自らの意思で代表者を選ぶという貴重な体験のお手伝いができるよう、選挙管理委員会で投票箱や投票記載台の貸出を行っています。
⇒「投票箱・記載台の貸し出し」
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ




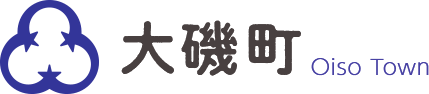

 PCサイトを見る
PCサイトを見る
更新日:2025年03月26日