大正14年7月6日
7月6日(月曜日)、午前8時出勤。
日曜日に、神奈川県測候所長測候技師の高木健と、同県農林主事補の禿包芳の両名が来場し、大磯測候所で、土地の件につき調査された。
午後1時半頃、中西土木委員は、長島書記と共に火葬場建築を踏査した。
午後4時頃、平塚新宿の民友社新聞記者が来場した。暑中見舞の広告料が金5円だった。大磯町代表として町長宮代新太郎・同助役小見忠滋の名義を出すことを町長は承諾した。交際費より支給する予定である。
午後5時に退庁した。
解説
今日は、県測候所の技師等が来て調査をしたようです。日本における気象観測は、明治5(1872)年函館で始まりました。明治8(1875)年には、東京気象台が設けられ、本格的な気象観測が始められました。続いて全国各地に測候所が設けられ、官庁や軍事施設をはじめ、学校や神社などにも、観測地点が置かれていたようです。明治31(1898)年1月、大磯小学校が観測所になったという記録があります。助役日誌に書かれた「大磯測候所」とは、そのことを言っているのかもしれません。学校が大震災で被災したため、新たな場所を探したのでしょうか。
また、今日は、新聞社に広告掲載を依頼しています。メディアが限られていた当時、新聞の影響力は大きかったと思われます。
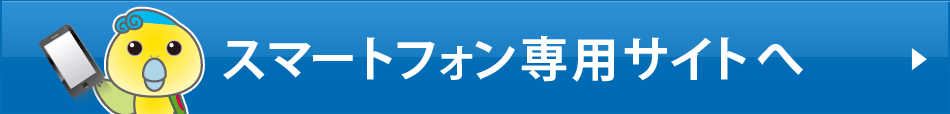







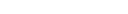
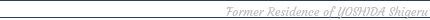




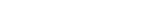



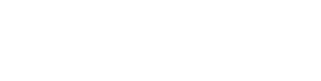
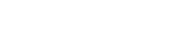
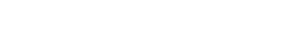



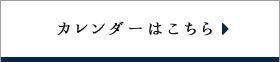
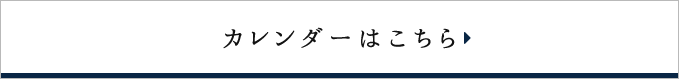
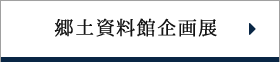
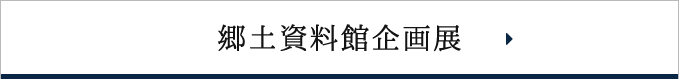
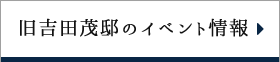
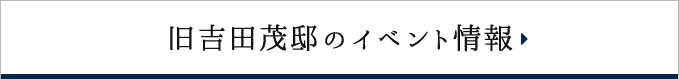
更新日:2025年06月19日