大正14年5月5日
5月5日(火曜日)、午前8時20分出勤。
本日は、栢木書記に会議録を作らせて進達した。
午後0時半頃、霜島校長を訪ね、来る10日の銀婚式御奉祝について協議の上、町役場・学校・在郷軍人分会・消防組・青年団・処女会等併合して、大磯小学校内において遥拝式を行うことにした。当日は、各戸に国旗を掲揚することにした。午後1時半に帰場した。
去る3日日曜日、神奈川県町村長の第6回通常総会を逗子小学校の講堂で開いた。中郡の出席村長は、大磯・土澤・東秦野・豊田・城島・伊勢原・岡崎・金田・吾妻・大野の10ヶ町村だった。金子会長の開会の辞、勅語奉読(大正12年11月10日の勅語)、会長朗読、知事代安藤地方課長の告諭、三浦郡長祝辞、三浦郡より銀婚式賀表を県下町村長会より奉呈の動議を提出した。満場一致で可決され、会長に一任することとなった。12時に休憩し、昼食をとった。午後0時45分に再開した。逗子小学校長である荒井氏による逗子町についての歴史的な講話と、東大教授の上杉博士による有益な講演があった。終了後、役員の選挙に移り、会長は留任し、副会長には城島村長と厚木町長が就任した。
解説
「銀婚式御奉祝」とは、大正天皇・貞明皇后の結婚25周年を祝う日のことです。お祝いとして、天皇・皇后の写真を入れた記念絵葉書が作られたことが知られていますが、町でも小学校で遥拝式をしたり、家々の軒先に国旗を掲揚することにしたようです。
今日の小見助役は、町長が不在の中で代理として出席した町村長会の報告を書いています。2日後になってしまったところに、忙しい様子が垣間見えます。また、この日の式次のなかに、勅語奉読(大正12年11月10日の勅語)があります。これは、関東大震災の直後で、大正天皇の名で摂政宮(皇太子裕仁)が発した「国民精神作興ニ関スル詔書」のことです。大震災と、その後の恐慌により、人々が動揺し国家的危機を招く恐れがあるとして、国家統合を図る目的で発せられました。会場の逗子小学校は、当時の正式名称は逗子尋常小学校で、明治5(1872)年に開校した歴史のある学校です。ここで講演をした上杉博士とは、憲法学者の上杉慎吉のことと思われます。彼は「天皇主権説」を唱えたことで知られています。このような場で勅語を奉読したことや講演の内容などを考えると、国家統帥の気運が徐々に高まって行く様子を、日誌の中からも感じます。
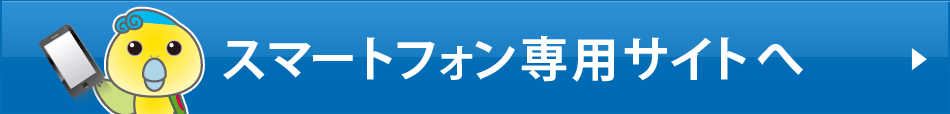







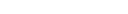
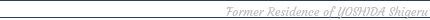




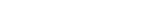



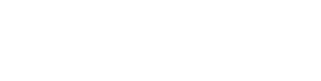
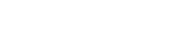
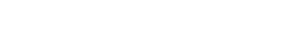



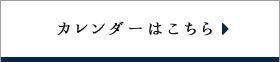
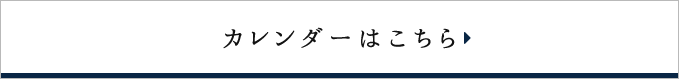
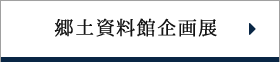
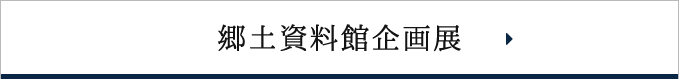
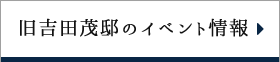
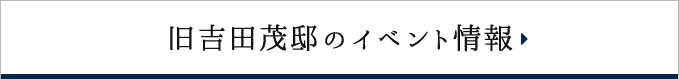
更新日:2025年04月03日