100年前の大磯 関東大震災特集13 地方金融に与えた影響
9月1日の関東大震災により金融機関は日本銀行をはじめ多くの本・支店の店舗が、火災での焼失や建物崩壊の他、融資の際の担保物件や有価証券の滅失等によって、甚大な損害を受けました。 震災直後、政府から緊急勅令が出され、取付け騒ぎ等への対応が取られています。
国の対応
まず、震災直後には、店舗などが物理的な被害を受けたため、被災地の多くの銀行は休業を余儀なくされました。そのような中、9月7日には、緊急勅令によって支払猶予令(勅令第404号)が公布されます。これは、9月1日以前に発生し、9月30日までの間に支払わなければいけない債務について、被災地域の企業・住民が債務者となっているものについては、30日間その支払を延期するというものでした。一方、給料・賃金等の支払のための払出や、預金者の1日100円までの払出は、対応しなければなりませんでした(勅令第404号第2条)。この勅令に応じて、横浜正金銀行などの7つの銀行は9月8日に開店、9月17日、18日頃までには東京の銀行のほとんどは開店し、横浜でも地元の銀行が9月28日には開店しました。
一方、9月27日には、日本銀行震災手形割引損失補償令(勅令第424号)が公布されます。これは、震災手形(震災地を支払地とする手形、震災地に営業所などを持っている者が振出した手形などの震災地関係の手形)が支払猶予期間終了後に決済不能となって経済活動が停滞する懸念があったため、これらの手形を日本銀行が再割引し、これによって日本銀行が損失を被った場合は、政府が1億円まで補償するというものでした。この震災手形の再割引期間は、当初、大正13年(1924)3月末まで(書換手形は大正14年9月末まで)とされましたが、震災手形の回収が進まなかったため、昭和2年(1927)9月末まで延期されました。再割引された手形は約4億円に上り、昭和2年の金融恐慌の糸口ともなりました。
関東大震災に苦しんだ大磯銀行
さて、それでは、当時、大磯町内にあった銀行は、どのような影響を受けたのでしょうか。当時、町内にあった銀行は大磯銀行と関東銀行大磯支店です。
大磯銀行と言えば、町内の名士が明治33年(1900)に開設した地元の金融機関です。ただ、震災前からその経営には黄色信号が点灯していました。
大正8年(1919)、第一次世界大戦の大戦景気で大磯町の別荘地価が高騰し、大磯銀行は不動産を担保に貸付額を増加させます。翌大正9年は、反動恐慌により土地バブルが弾けて、不動産担保貸付の回収が進まず、貸金の固定化と債権の不良化が経営に影を落としました。大正10年、政府や県の恐慌対策として小規模銀行間の合同・合併を模索するも合意に至らず、6月5日、大磯銀行は資本金を50万から100万円に増資することを決定します。このように、第一次世界大戦の影響による好不況の落差にうまく乗り切れなかったまま、大正12年9月1日の関東大震災を迎えることとなりました。
関東大震災後、大磯銀行は、その後の立て直しが困難となり、ついに、12月3日に休業します。
大磯銀行、駿河銀行に買収される
大磯銀行の休業を受け、12月16日には、中郡長が主催する、大磯銀行休業の対策協議会が開かれました。この協議会には、大磯町長や、石塚大磯銀行取締役らが出席しました。また、年が明けた大正13年1月27日、預金者大会で預金者100名余りが、大磯銀行の重役に説明を求めます。そして翌2月には、銀行の諸帳簿の不整理が発覚し、預金者が大蔵省へ陳情する事態へ発展、大磯銀行の石塚取締役は、駿河銀行へ救済を求めました。その後も、預金者による陳情が繰り返されますが、11月28日に駿河銀行との売買譲渡契約が交わされ、大正15年(1926)7月4日には、大磯銀行の払出し紛糾は解決、7月15日には駿河銀行への買収が成立しました。3年程もかかった交渉でしたが、預金者への払戻しは元金の2割強にとどまり、預金者にとっては残念でとてもつらい厳しい結果となりました。
同じく、大磯町内にあった関東銀行も大正13年(1924)に破綻しており、震災が金融機関に与えた影響は大きいものでした。
次回は1月12日(金曜日)に更新します。隆起した海岸の復旧について、ご紹介します。
参考
- 佐々木哲也「大磯銀行の設立・展開とその破綻処理」(『大磯町史研究』第6号、1999年)
- 鈴木昇『大磯の今昔』(九)、2000年、p.105~107
- 『大磯町史新聞記事目録』第2集、2005年
- 『大磯町史』7、2008年、p.347~352、423~434
- 中央防災会議災害教訓の継承に関する専門調査会編『1923関東大震災報告書』第3編、2009年
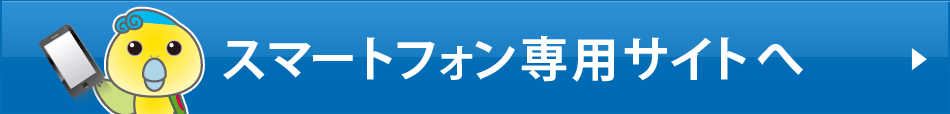







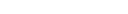
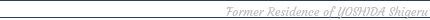




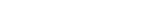



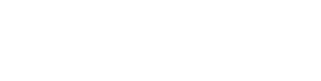
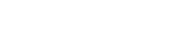
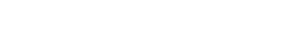



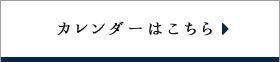
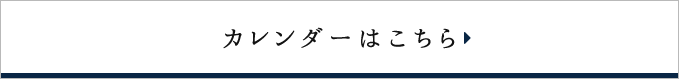
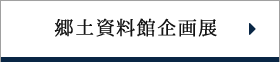
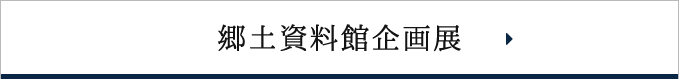
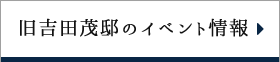
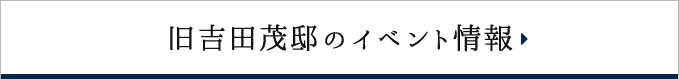
更新日:2024年01月05日