白岩神社の歩射の調査に行きました
今日は、白岩神社の歩射のお話です。
大磯町の西小磯地区には鎮守である白岩神社があります。
白岩神社では、3月の例大祭として「白岩神社の祭礼」(町指定無形民俗文化財)が行われます。
この祭礼では歩射行事が行われるのも、見所の一つです。
当該行事は弓を的と恵方の方角に射って豊作や豊漁を願う意味合いがあり、民俗学的には歩射(オビシャなどとも)といわれるものです。
この地が農作や地引網などの半農半漁で暮らしを立ててきたことが、背景にあるのでしょう。
今年は3月1日に準備作業と冷酒式が、2日に歩射行事が行われました。
※白岩神社の歩射については、以下のページでも紹介されています。
3月1日は朝から準備作業が行われていました。
社人と町内会の方たちで的に使う竹を削り、骨にしていきます。
あわせて弓も梅の木と麻のヒモを使って作っていきます。
この日は夕方に冷酒式(非公開)という式が行われました。

的に使う竹を削っていきます

みんなで削ります

私も削るのに参加させていただきました

弓も作ります

削った竹を組み合わせて的の骨を作ります

組みあがったので、半紙を貼るための糊をぬります

半紙をはります

半紙を切り、的の中心部を描いていきます

完成です
祭礼当日は12時30分に宿である西小磯東老人憩いの家を出て、13時から白岩神社で式典が行われます。

憩いの家から白岩神社に向かいます
式典後は歩射が行われました。
一列に並んだ状態で社殿を右回りに3回周り、参道に用意された的のところまで下りていきます。
的のところでも右回りに3回周り、3回目に的に向かって射ちます。
弓持ち2人が各々2本の矢を持ちます。一番矢が的を射ってから、あとの1本はアキの方(恵方)へ射ます。二番矢も同様にします。
終わると行列は社殿に戻っていきました。
射終わった的は解体され、魔よけとして参詣人たちに配られました。

白岩神社から降りてきました

的に向かって射つ様子

的を解体しています
この祭礼で興味深く感じたのは、伊藤博文が祀られることです。
白岩神社の本殿脇には祠(藤公神社)があり、白岩神社の祭礼の間は伊藤博文のブロンズ像が祀られているのです。
滄浪閣があったことで、地元の人々とも交流があったといいますが、そうした実在の人物が神格化され、神として顕彰されているのを民俗学では「人神信仰」としてとらえてきました。
伊藤博文は人神信仰の事例の一つとして考えることができます。

伊藤博文のブロンズ像が並んでいます
白岩神社の歩射祭礼は昭和40年代にも調査が行われており、その記録によると社人には、一番オンベ・二番オンベ・弓持ち(2人)・鍵取り・留守居番(2人)・御膳所(3人)・太鼓という役割が割り振られています。また、この役割は基本的に世襲制で受け継がれています。
地域の風景や生業が変わるなか、豊作豊漁を願うこの行事はかつての西小磯の人々の暮らしのありようを思い起こさせてくれます。
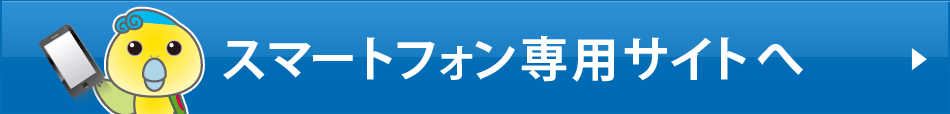







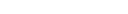
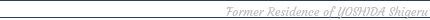




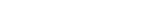



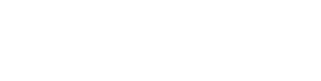
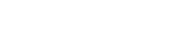
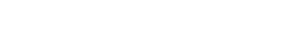



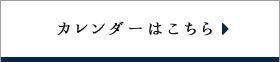
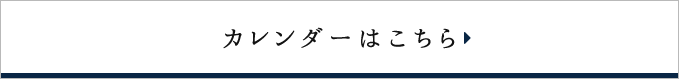
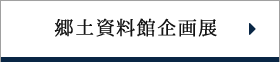
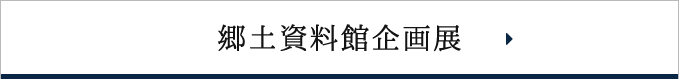
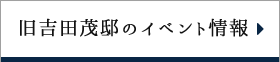
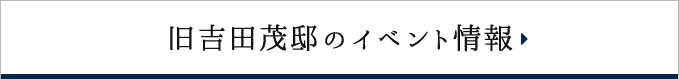
更新日:2025年07月25日