1-2 日清戦争
朝鮮半島の権益をめぐって1894年(明治27年)8月1日から始まった日本と清との戦争は、明治政府が遂行した初の本格的な対外戦争であった。すでに1888年(明治21年)より、陸軍は、鎮台制から外征軍としてより機動力の高い師団制に移行しており、日清戦争において、24万人余りの兵力を動員し、戦病死者は約13,000人にのぼった。
1896年(明治29年)に作成された「陸海軍人取調書」には、旧大磯町・国府村を含む中郡管内における、日清戦争に従軍した軍人が一覧で取りまとめられている。これによると、旧大磯町・国府村からの応召者数は計57名で、20歳の現役兵から30歳前後の予備役・後備役兵も召集されている。
出征先は主に台湾・澎湖島に18人、遼東半島に29人で、遼東半島への出征は、おそらく旅順口攻略を担った第2軍隷下の第1師団に所属していた兵士と考えられる。このほか日本国内にとどまっていた守備部隊に配備されている者もいた。また、戦死者は3名で、すべて台湾・澎湖島での戦闘によるものである。

日清戦争に従軍した清国北洋軍兵士の上衣
日清戦争に従軍した将校の装備
下の軍服は、日清戦争時に第3師団歩兵第18聯隊の中隊長を務めた将校のものである。
日清戦争当時の軍服は、1886年(明治19年)に制定されたものであり、左が平時及び戦時に着用する軍衣、右が儀礼などで着用する正衣である。これらの軍服には、襟章・肩章・袖章などで、階級や兵科がわかるようになっていた。
軍衣については、日露戦争後の1906年(明治39年)に濃紺色からカーキー色に改められ、形状も大幅に変更された。

画像の利用について
このページに掲載している画像の利用は、収蔵資料データベースの画像利用に準じます。詳しくは、リンク先をご確認ください。
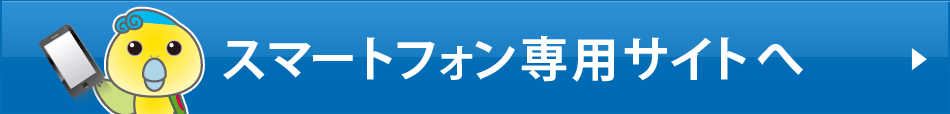







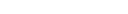
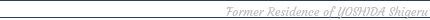




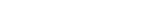



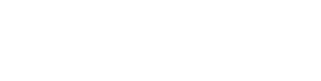
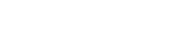
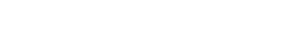



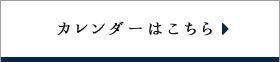
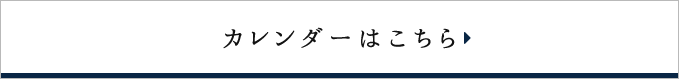
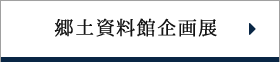
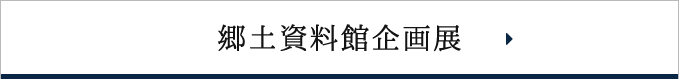
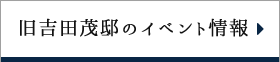
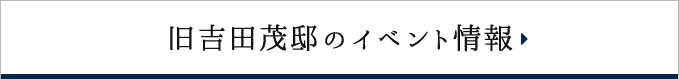
更新日:2021年10月22日