国民健康保険税
国民健康保険の被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費は、皆さんの保険税でまかなわれています。保険税は国民健康保険を支える大切な財源です。国民健康保険を健全に運営するため、保険税の納付をお願いします。
保険税について
納税義務者
国民健康保険税は世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者になります。(地方税法第703条の4第28項及び大磯町国民健康保険税条例第1条第2項に規定。)
保険税の算出方法
国民健康保険税は、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合計で算出します。
各項目の金額は、前年中(1月から12月)の所得から算定する「所得割(率)」と「均等割(額)」「平等割(額)」を足して求めます。
|
医療給付費分 (全員) |
後期高齢者支援金分 (全員) |
介護納付金分 (40~64歳の方) |
|
|---|---|---|---|
| 所得割 | 6.5% | 2.9% | 2.4% |
| 均等割(一人あたり) | 25,500円 | 13,500円 | 12,600円 |
| 平等割(一世帯あたり) | 21,000円 | - | - |
| 世帯限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
所得割の算定方法
所得割は、加入者一人ひとりの前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額に上記の税率を乗じて合算します。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
介護納付金分について
国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者で、当該年度内に65歳を迎える方は、加入期間の月割りで計算します。
年度途中で40歳になる方は、誕生月(1日の生まれの方は、その前月)上旬に上乗せ課税分を含む納付書を送付します。
年度の途中で加入・脱退された方
年度の途中で加入した方の保険税は、加入の届出をした月に係わらず、国民健康保険に加入した月(会社を退職した日の翌日、町外から転入した日などの属する月)から月割計算をします。
また、年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分を月割計算します。
それぞれ手続きをした月の翌月以降に「更正決定通知書」を送付します。
大磯町に転入してきた方
他市区町村から大磯町に転入してきた方の保険税は、まず「平等割額」と「均等割額」で納めていただく場合があります。その後、大磯町から転入前の市区町村に問い合わせをし、所得判明により保険税額が変わる場合は、変更後の金額で納めていただくことになりますので、再度通知書を送付します。
保険税の軽減について
低所得世帯に対する軽減
所得の申告(確定申告、町県民税の申告、国民健康保険の所得申告のうちいずれか)がお済みで、世帯の国民健康保険加入者の合計所得が軽減の基準となる額以下の方は、均等割と平等割が軽減されます。
なお、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、軽減判定は世帯主の所得も含めて判断します。
また、世帯の国民健康保険加入者のうち、どなたか一人でも申告がない場合は、軽減ができません。
| 軽減割合 | 軽減の基準となる額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(29.5万円×加入者・特定同一世帯所属者の数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(54.5万円×加入者・特定同一世帯所属者の数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
注意)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
注意)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金所得者(公的年金等の収入が、65歳未満は60万円を超える方、65歳以上は110万円に特別控除15万円を加えた125万円を超える方)です。
未就学児に係る均等割の軽減
令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が2分の1軽減されます(申請の必要はありません)。
低所得世帯に対する軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、軽減措置後、さらに均等割額を2分の1軽減することになります。例えば、7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割についても2分の1軽減するため、合わせて8.5割の軽減になります。
保険税(均等割額)の軽減割合一覧
| 所得の基準による軽減 | 未就学児以外の方の軽減割合 | 未就学児の方の軽減割合 |
|---|---|---|
| 7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
| 5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
| 2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
| 軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の緩和措置
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、次の緩和措置を講じます(申請の必要はありません)。
軽減判定についての措置
国民健康保険税の軽減判定の際、所得・世帯構成に変更がない限り、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得及び人数も含めて判定をします。
平等割額の軽減措置
後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の被保険者が1人の世帯になる場合は、平等割額を5年間は2分の1の額、その後3年間は4分の1の額を軽減します。
健康保険組合(社会保険等)の被扶養者であった方に対する軽減
健康保険組合等に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方が国民健康保険に加入した場合、申請により減免措置が受けられます。
対象者
次のすべてに該当する方
- 会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
- 加入時点で65歳以上75歳未満の方
注意)国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方は該当しません。
所得割額についての軽減措置
全額免除(当分の間)
均等割額についての軽減措置
半額減免(国民健康保険加入後2年間)
平等割額についての軽減措置
半額減免 (被保険者が1人の場合、国民健康保険加入後2年間)
保険税を滞納した場合
督促状・延滞金・訪問納付勧奨について
納期限までに保険税が納付されない場合、督促状を送付します。納期限を過ぎてから納付された場合は、納付されていても、行き違いで督促状が届く場合がありますので、ご了承ください。滞納の状況によっては、直接職員がご自宅に伺い、納付を勧める場合もあります。
保険税の使いみち
国民健康保険に加入していると、病気にかかったときやけがをしたとき、国民健康保険被保険者証を病院等の窓口に提示することで、診療・治療の保険適用分について保険給付が受けられます。また、加入者が出産したときの「出産育児一時金」や死亡したときの「葬祭費」を申請することができます。
令和4年4月1日からキャッシュレス納付がはじまりました!!
便利・簡単・確実な口座振替について
納め忘れのリスクを減らすために口座振替を活用しましょう。口座振替であれば、納め忘れや延滞金のリスクを避けられます。さらに、保険税の還付金が発生した際に、振替口座にお返しするので、詐欺等の心配もありません。口座振替依頼は大磯町役場、国府支所及びお近くの取り扱い金融機関で簡単に手続きができます。
口座振替申し込み方法について
- 預金通帳
- 印鑑(通帳届出印)
- 国民健康保険税納税通知書
- 大磯町歳入金等口座振替依頼書兼ゆうちょ銀行自動払込利用申込書(以下口座振替依頼書)
これらをもって、町役場窓口、国府支所窓口または町指定の金融機関で手続きをしてください。
なお、口座振替依頼書が金融機関に設置されていない場合は、電話やメールにてお申し出いただければ、指定の宛先まで郵送いたします。
取り扱い金融機関等について
- さがみ信用金庫
- 湘南農業協同組合
- スルガ銀行
- 中栄信用金庫
- 中南信用金庫
- 平塚信用金庫
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- ゆうちょ銀行
- 横浜銀行
その他
一度申し込みをされた口座振替登録は、変更または廃止の届出がない限り、翌年度以降も継続します。
また、世帯合併や世帯分離などで国民健康保険の世帯主が変更になった場合、納税義務者が変わりますので、再度口座振替のお申し込みが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ




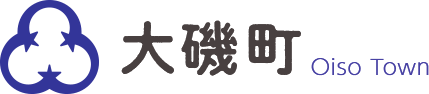

 PCサイトを見る
PCサイトを見る
更新日:2024年12月02日