教育委員会の構成
教育委員会の構成
教育長

府川 陽一(ふかわ よういち)
令和6年4月1日付けで教育長を拝命しました府川陽一(ふかわよういち)です。
教育基本法が示す「教育の目的」、学校教育法が示す「義務教育の目標」に基づき、「学校教育」が全国で実施・展開されているところですが、実施されているからといって、子どもたちが生き生きとした学習活動を行い、子どもたちに生きる力がしっかりと身についているとは必ずしもいえるわけではありません。
「基礎的な知識や技能の習得がなされているか」「習得した知識等」を活用して「思考力」「判断力」「表現力」等の能力が育まれているか、そして何より「主体的に学習に取り組む態度」が養われているのかと問われると、正直、大変心もとないのが、大磯町に限らず全国各市町村の偽らざる実態であるかと思われます。
私は、その実態から目を逸らすことなく、特に以下の3点について、力を注いでいきたいと考えています。
まず1つ目は、「授業の質の向上」です。私がよく見た授業風景ですが、例えば、「鉛筆は机に置いて」「手は膝に」「目は先生の顔」「お口はチャック」と先生が指示する。でも、多くの子どもたちはベチャクチャ喋ったまま。そこで、先生が大きな声で「静かにしなさい!」と注意する。しかしそれでも数人の子どもたちは楽しそうにおしゃべりを続ける。いよいよ先生は怒りだして「何回言ったらわかるんですか!」「先生の言うことを聞きなさい!」・・・
そんなことが毎時間繰り返される教室。・・静かにさせたくて、逆に話し続け、指示を出し続ける先生。授業の遅れを気にして、結論を急ぐ先生。○か×か、正しいか正しくないかの決まった答えばかりを求めてしまう先生。・・いつの間にか、教師中心の一方的押しつけ授業になってしまっている「追い立てられるような」「息が詰まる」教室。・・
教師主導の一方的な一斉授業は今すぐに改善されなければなりません。子どもの話をじっくり聴いたり、子どもへの問いかけを丁寧にしたりして子どもと一緒に考える先生。そうした先生なら、例えば、漢字練習のドリル学習とかワンポイントレッスンとか、細切れの多様な学習活動があったとしても、子どもたちはきっとついてくるはずです。今すぐ変わらなくてはならないのは、干からびた「ワンパターン授業」に他なりません。
授業改善に完成はありません。先生方に子どもたちをワクワクドキドキさせるような授業をぜひつくってほしいと心から願っています。
2つ目は「体験活動の充実」です。
生きる力を養うには、体系的で組織的な教育、かつ、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視した教育課程の用意が必要ですが、加えて体験的な学習が不可欠です。家庭での生活体験(買い物とか掃除とか料理のお手伝い、ゴミ処理とか身の回りの整理整頓とか)を積み重ねること、また、日常生活ではあまり経験できないボランティア活動などの社会体験活動と社会奉仕活動、自然体験活動などを、学校、家庭、地域が一体となって学校教育活動の中に無理なくバランスよく位置付けていきたいものです。(=地域とともにある学校の創造)
さて、その際、教師も子どもも、「MUST」ではなく「CAN」の姿勢を貫いていきたいものです。すなわち、「○○しなければならない」という観念から自らを解き放ち、「こういうことなら、私にもできる」「あなたと一緒ならチャレンジしてみたい」というように、自分からチャレンジする意欲を奮い立たせることが何よりも大事です。受け身ではなく、失敗を恐れずに、前向きに行動してみることが望まれます。「認め合う」「比べない」「心を込めてひたすら努力する」「自分を鍛える」「心の財産をつくる」・・そんな自学自習・自問自答・自給自足の学習習慣をぜひ身につけていきたいものです。
最後の3つ目は「子どもたち自身の学校生活の充実」です。
子どもたちにとって、学校という場は生活の場でもあります。休み時間・昼休み・放課後・部活動時・登下校時など、「教師の目の届かない所で」友だちと自由にコミュニケーションをとる場でもあります。子どもにとっては大人に管理されない情報センターにもなります。いわば、「無意識に学べる」心ときめく貴重な学びの場となります。しかし、同時にいじめが起こったりする場にもなり得ます。
そんな中で児童生徒の安心安全をどう確保するのかが問題となりますが、教師を含め大人たちが見守り続けなくてはなりません。「見て見ぬふりをする」など決して許されません。教師も親も子どもも、「いじめの未然防止」をする責務があります。「いじめ防止対策」を徹底すべきです。目配り気配り予兆察知と一人ひとりの命を守る勇気が欠かせません。
健全な人間関係が形成されるよう、子ども集団、保護者、学校職員の風通し、コミュニケーションを日頃から良好にしておくことが肝要です。教師を含め大人社会全体で子ども集団からストレスを取り除くことが求められています。
微力ではございますが、今まで得た経験を存分に生かし、私自身が生まれ育った郷土大磯の教育環境の充実のために力を尽くしたいと思っています。
(任期:令和6年4月1日~令和9年3月31日)
委員(教育長職務代理者)

トーリー 二葉(とーりー ふたば)
令和4年3月17日付けで教育委員を拝命し、2期目を迎えましたトーリー二葉です。
私が育ちました、我が大磯町で将来を担う子どもたちの教育にかかわる機会をいただきましたこと感謝いたします。
教育環境が大きく変わる中、子どもたちには自立、責任、感謝、他者とのかかわり方をしっかり考え、「人間力」を高めて欲しいと願っています。また、大磯町の歴史、文化を学び自分の住んでいる、この大磯町を誇りに思って欲しい、そして海と山に囲まれた自然豊かな環境で、地域に見守られながら心身ともに大きく大きく成長していって欲しいと思います。
大磯町の、そして国の宝である子どもたちの教育に関して、私のPTA、子ども会等での活動の経験を生かした、保護者目線での考えが役立てば幸いです。
そして教育現場、地域、子どもたちの声に耳を傾け、様々な課題に向き合っていきたいと思います。
未だ未だ学ぶことばかり、日々勉強ですが、子どもたちの教育環境の充実のため、微力ではございますが力を尽くしてまいります。
(任期:令和4年3月17日~令和8年3月16日)
委員

櫻田 京子 (さくらだ きょうこ)
令和7年2月17日付けで教育委員を拝命した櫻田京子です。
これまで、神奈川県立高等学校の教育に携わり、大学や教職大学院で教員養成に関わってきました。
大磯町民として、町内の教育活動に少しでもお役にたてれば嬉しく思います。
令和5年11月に大磯の教育ビジョン「大磯わくわくプラン」が策定され、大磯町の教育が進められているところです。
まず、学校は子どもたちが安心して楽しく通学したいと思える場所であるべきです。
社会の急激な変化もあり、令和4年12月に文部科学省は「生徒指導提要」を改訂し、何かの問題が起こってからの対応よりも、むしろ子どもを成長させる指導や未然防止・早期発見を重視する指針を示しています。
子どもたちが「お互いを尊重する雰囲気」を醸成することや大人は子どもの小さな変化に「気付く」ことが大切です。
また、現行の学習指導要領の学びでは、子どもにとっての「主体的・対話的で深い学び」「個別最適な学び」「協働的な学び」が追求され、各学校はさまざまな工夫を凝らしています。
「ご家庭や地域、学校が協働して子どもたちを育てている町」と誰もが誇れる教育を進めたいと存じます。
(任期:令和7年2月17日~令和11年2月16日)
委員

武沢 護(たけざわ まもる)
令和7年4月1日付けで教育委員を拝命しました武沢護です。
青い空、青い海そして緑豊かな丘陵と全国に誇る自然環境をもつ大磯。この大磯の子どもたちが心豊かに育つ環境、また町民が生涯に渡って学ぶことができる環境づくりのため教育行政の充実を目指し、地域住民との協力を通して教育環境のさらなる充実を目指したいと考えています。
わが国は少子高齢化を迎え、学校教育そして生涯教育は様々な課題を抱えています。ここ大磯も例外ではありません、自由・平等そして平和な社会の実現に向けて教育はこれからの時代を切り開くための最重要課題です。
私と我が家の二人の子どもはこの大磯の教育を受け、育ちました。大磯の教育行政が全国のモデルになるよう、微力ではありますが、私の教育に関わる経験が少しでもお役に立てればと考えています。
(任期:令和7年4月1日~令和9年9月30日)
委員

鈴木 孝善(すずき たかよし)
長年の教員生活や、その後の民生委員・児童委員を経験する中、多くの方に出会い、支えていただきました。そこで学び感じたことを大磯の教育に少しでも生かせればと思っています。
大磯の豊かな自然や歴史ある文化の中で、子どもたちが「よく学びよく遊び」生き生きと活動できる学校や地域の教育環境の充実が図られることを願っています。
また、これから世界は、大きく変化し予測のつかない社会になり、人々の考え方や生活環境も変わってきます。子どもたちには、共感力、課題解決力、実行力、判断力などの力をつけ健やかに成長してほしいと思います。
(任期:令和7年4月1日~令和8年3月16日)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課 教育総務係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:322,328,332)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ




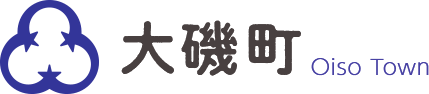

 PCサイトを見る
PCサイトを見る
更新日:2025年04月01日